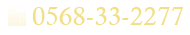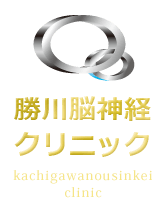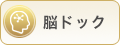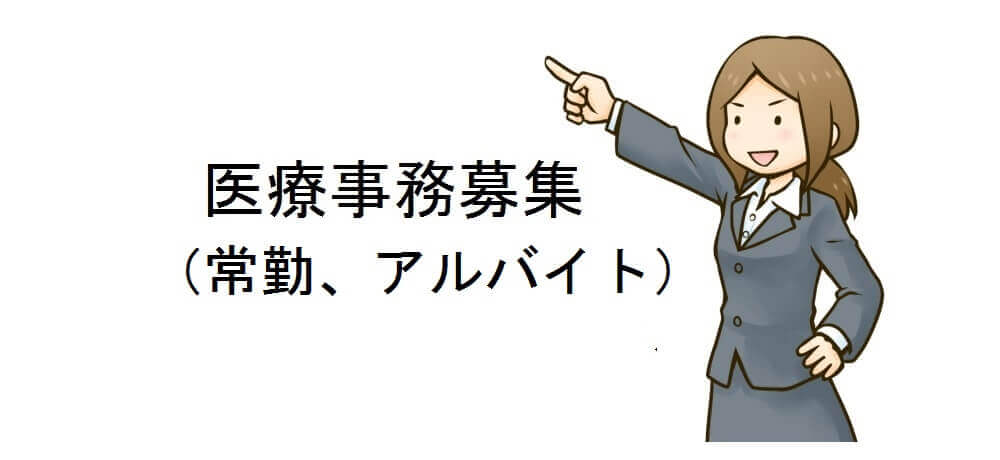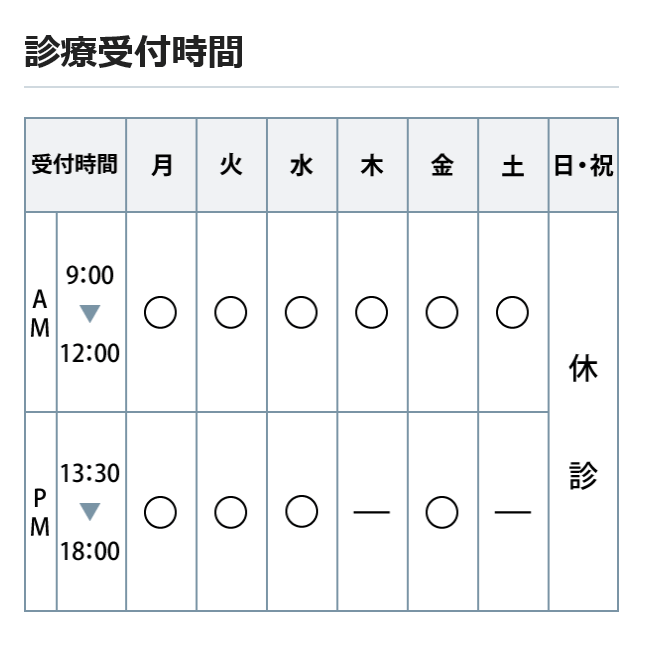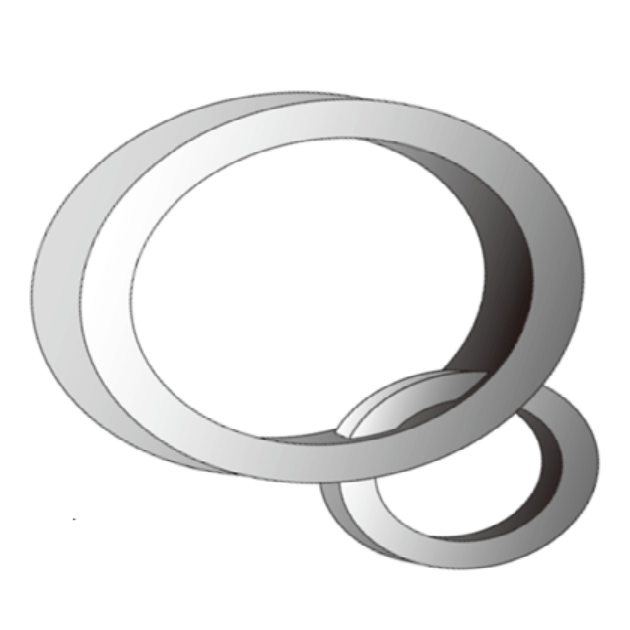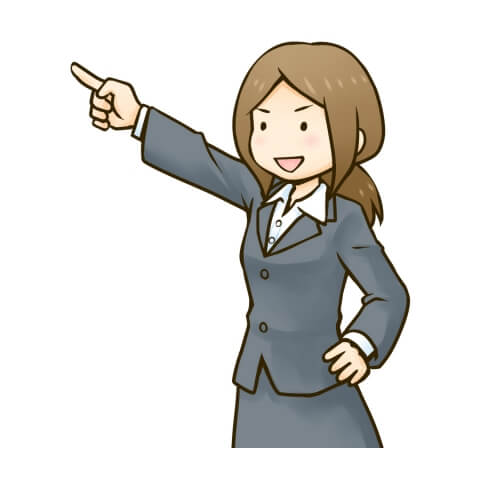HOME > Information > Woven EndoBridge(WEB)とは|開頭せずに治療できる脳動脈瘤の新しい選択肢 | 名古屋~春日井の脳神経外科 | 勝川脳神経クリニック
Woven EndoBridge(WEB)とは|開頭せずに治療できる脳動脈瘤の新しい選択肢
Woven EndoBridge(WEB)治療の基本概要
Woven EndoBridge(WEB)とは、開頭手術を行わずに脳動脈瘤を治療できる、最先端の血管内治療デバイスです。
特に「広頚性脳動脈瘤」や「分岐部動脈瘤」に対して、従来のコイル塞栓術では治療が困難だったケースにも対応可能な新しい選択肢として注目されています。
Woven EndoBridge(WEB)の仕組みと特徴
WEBは、メッシュ状のニチノール(形状記憶合金)製のデバイスで、動脈瘤の内部に展開され、血流を遮断することで動脈瘤内の血液の流れを止め、自然な血栓形成を促進します。これにより、動脈瘤の破裂リスクを根本的に抑えることができます。
- ✅ 特徴的なポイント
- ・開頭せずに治療が完結(低侵襲)
- ・ステント不要で抗血小板薬の長期使用を回避できる場合もあり
- ・動脈瘤内部からのアプローチで周辺血管への負担が少ない
- ・1回のデバイス展開で治療が完結する可能性も期待できる
- ・短時間の手術で済むことが多く、入院期間も短縮
- ・再出血や再治療のリスクが低いとする報告もあり
なぜWEBが注目されるのか
脳動脈瘤は、破裂すればくも膜下出血などの致命的な脳血管障害を引き起こす可能性がある疾患です。従来は以下のような治療法が中心でした。
- ➤ 開頭クリッピング術
- 外科的に動脈瘤をクリップで遮断
- ➤ コイル塞栓術
- 動脈瘤内にプラチナ製のコイルを詰めて血流を遮断
- ➤ フローダイバーター
- 動脈瘤周囲の血流を制御するステント型デバイス
しかし、これらの方法では広頚性(ネックが広い)や分岐部にできる動脈瘤に対しては治療が困難なケースも多く、再発や再治療が課題でした。WEBでは、従来の治療が難しかった広頚性や分岐部の動脈瘤にも対応可能な点が注目されています。
適応となる脳動脈瘤の種類
📌 適応詳細:
前方循環系又は後方循環系の分岐部に位置する、
ワイドネック型(ネック部が4mm以上又はドーム/ネック比が2未満と定義)の
頭蓋内動脈瘤に対する血管内治療に使用されます。
Woven EndoBridgeの具体的な適応部位としては、以下のような分岐部動脈瘤が含まれます。
- ➤ 前交通動脈瘤(ACom)
- 前交通動脈に位置する動脈瘤で、解剖学的な構造が複雑なため、治療が難しいとされています。
- ➤ 中大脳動脈分岐部動脈瘤(MCA Bifurcation)
- 中大脳動脈の分岐部に位置する動脈瘤で、従来の治療法では難易度が高いとされていました。
- ➤ 内頚動脈先端部動脈瘤(ICA Terminus)
- 内頸動脈の末端部に位置する動脈瘤で、血流の分岐が複雑なため、治療が困難なケースがあります。
- ➤ 脳底動脈先端部動脈瘤(Basilar Top)
- 脳底動脈の頂部に位置する動脈瘤で、後方循環系に属し、治療が困難な部位の一つです。
これらの部位は、分岐部に位置し、かつワイドネック型の特徴を持つため、WEBデバイスの適応となる可能性があります。 ただし、適応の可否は動脈瘤の形状や位置、患者さんの全身状態などを総合的に判断する必要があります。
ワイドネック型の脳動脈瘤とは
ワイドネック型(広頚性)脳動脈瘤とは、動脈瘤の「入り口(首の部分=ネック)」が広く、ふくらみの底(ドーム)に対して比率が高いタイプの脳動脈瘤を指します。
なぜ「ワイドネック型」は注意が必要?
通常の動脈瘤に比べ、ワイドネック型は以下のような点で治療が難しくなります。
- ➤ コイルが動脈瘤の外へはみ出しやすい
- 塞栓中にコイルが正常血管側に逸脱するリスクがある
- ➤ 周囲の正常な血流を妨げるリスクがある
- 特に分岐部での治療は血行動態の影響が大きく注意が必要
- ➤ 分岐部にできやすい
- 脳の主要な血管の分岐に好発し、治療が難しいケースが多い
ワイドネック型に適した治療法とは?
従来の「コイル塞栓術」だけでは塞ぎきれない場合も多く、次のような治療法が検討されます。
- ➤ ステント併用コイル塞栓術
- 血管内に金属の網状チューブを配置し、コイルの逸脱を防ぐ方法
- ➤ フローダイバーター
- 血流そのものを変えて動脈瘤を自然に閉塞させるデバイス
- ➤ Woven EndoBridge(WEB)治療
- 動脈瘤内部に特殊なデバイスを展開し、内部から血流を遮断
これらは、動脈瘤の位置や大きさ、形状、患者さんの体調などを総合的に判断して選択されます。
WEB治療のメリットとデメリット
- ✅【メリット】
- ➤ 低侵襲:開頭をせずに治療が完了
- ➤ 短時間での手術可能:30分~1時間程度で完了するケースもある
- ➤ 合併症リスクが比較的低い
- ➤ 抗血小板薬の使用が最小限に抑えられる可能性あり
- ➤ 治療後の経過観察で良好な完全閉塞率
- ✅【デメリット・注意点】
- ➤ 動脈瘤の形状によっては適応外となることがある
- ➤ 国内では治療可能な施設が限られている
- ➤ 治療費が高額となる場合がある(保険適用の条件に注意)
Woven EndoBridge(WEB)は脳動脈瘤治療の新時代へ
Woven EndoBridge(WEB)は、広頚性動脈瘤や分岐部動脈瘤に対して、これまでの治療の限界を打ち破る可能性を持つ革新的なデバイスです。低侵襲で合併症も少なく、かつ確実な閉塞を目指せるWEB治療は、今後ますます注目される治療法の一つといえるでしょう。
すでに欧州を中心に10,000症例以上の実績があり、臨床データも蓄積されています。日本では2020年以降に治験・承認が進み、現在は限られた専門施設のみで対応可能な最先端治療とされています。WEB治療に対応可能な医療機関は限られているものの、今後の標準治療の一角を担うことが期待されています。
🔴主な評価ポイント🔴
- 📌 WEBデバイスによる完全閉塞率
- ➤ 70~85%
- 📌 再治療率の低下
- ➤ 初回治療の成功率が高く、再手術の必要が少ない
- 📌 術後出血合併症のリスク軽減
- ➤ 血流遮断の精度が高く、安全性に優れるとされる
よくある質問(FAQ)
- 📌 Q1. WEBと通常のコイル塞栓術の違いは?
- ➤ WEBは「動脈瘤の中にデバイスを一体型で展開する」構造のため、塞栓効果が早く、再発率が低いとされます。
➤ また、ステントを併用しないケースが多く、抗血小板薬が不要または短期で済む点も違いです。 - 📌 Q2. 治療は保険適用ですか?
- ➤ 一部の施設・条件下では保険適用が認められていますが、すべての症例が対象ではありません。
➤ 主治医や専門医と相談し、適応判断を受けることが重要です。 - 📌 Q3. 治療後は通院が必要ですか?
- ➤ 術後1〜3ヶ月ごとに画像評価(MRIや血管撮影)を行い、閉塞の進行状況や再開通の有無を確認します。
一般の方向けのやさしい解説
- ➤ 脳動脈瘤とは
- 脳動脈瘤(のうどうみゃくりゅう)は、頭の中の血管がふくらんで風船のようになったものです。
- ➤ くも膜下出血のリスク
- 風船が破裂することで、「くも膜下出血(くもまくかしゅっけつ)」という、命に関わるような出血を起こします。
- ➤ 早期発見と検査
- 予防、検査としては、破裂前に脳動脈瘤を見つけることが大事で、MRI/MRAで検査することになります。
- ➤ 治療の対象となる脳動脈瘤
- 主に5mm以上の脳動脈瘤に対して、破裂しないように治療が行われます。
- ➤ 主な治療法の種類
- 治療法には開頭クリッピング手術とカテーテル治療(コイル塞栓術)があります。
- ➤ 開頭クリッピング手術
- 頭の骨を開けて、動脈瘤をクリップで止める方法
- ➤ カテーテル治療(コイル塞栓術)
- 足の付け根からカテーテルを入れて、動脈瘤の中にコイル(細い金属)を詰めて、血液が入らないようにする方法
✅ これらの治療は、多くの動脈瘤で効果がありますが、ふくらみの入り口が広い(=広頚性)場合や、血管が分かれている場所にある場合には、治療が難しいこともあります。
📌 新しい治療法「Woven EndoBridge(WEB)」とは?
Woven EndoBridge(WEB)は、頭を開けずに、カテーテルだけで治療を完結させる、最新の治療法です。
WEBは、とても細かい金属のメッシュでできた小さなカゴのようなものです。
これをカテーテルを使って、脳動脈瘤の中に入れて広げることで、ふくらみの中に血液が流れ込むのを止めてしまいます。
すると、自然にその中に血が固まり(血栓)、時間がたつと動脈瘤は閉じていきます。
📌 どんな人がWEB治療の対象になるの?
特に次のようなタイプの脳動脈瘤の方に向いています。
- ふくらみの入り口が広い(広頚性)動脈瘤
- 血管が分かれている場所にできている動脈瘤(分岐部)
- コイルでは中にうまく詰められなかったケース
ただし、すべての動脈瘤に使えるわけではなく、血管の形や位置によって向き不向きがあります。
主治医の先生が、画像検査をもとに適応を判断します。
📌 日本でも治療できるの?
はい、日本でもこのWEB治療は2020年代から導入されはじめ、少しずつ治療できる病院が増えてきました。
ただし、全国のすべての病院で受けられるわけではなく、専門の医師や設備がある医療機関に限られます。
📌 WEBは、将来の主流になるかもしれない治療法
Woven EndoBridge(WEB)は、これまで治療が難しかったタイプの脳動脈瘤にも対応できる、新しい可能性を持った治療法です。
まだ治療できる病院は限られていますが、今後広がっていくと期待されています。
もし、あなたやご家族が「脳動脈瘤」と診断されて不安なときは、WEB治療が適応になるかどうかを主治医に相談してみてください。
重大な副作用・合併症について
Woven EndoBridge(WEB)は、低侵襲で効果の高い脳動脈瘤治療法として期待されていますが、全ての医療行為と同様に、一定のリスクや合併症が生じる可能性があります。
ここでは、WEB治療に関連して報告されている「重大な有害事象(重篤な副作用や合併症)」について、一般の方にもわかりやすく解説します。
- 📌【血管・治療操作に関わるリスク】(合併症、後遺症について)
- ➤ 挿入部位の血腫
カテーテルを挿入した太ももや腕の部分に、血のかたまり(血腫)ができることがあります。 - ➤ 血管解離または穿孔
血管が一部裂けてしまったり、器具で傷つけて穴が開いてしまう状態です。これにより出血や虚血が起きる場合があります。 - ➤ 血管閉塞・塞栓
血のかたまり(血栓)などが血管を詰まらせることで、脳への血流が遮断され、虚血性の症状を引き起こすことがあります。 - 📌【脳・神経に関する有害事象】
- ➤ 動脈瘤の破裂
治療中や直後に、脳動脈瘤が破裂するリスクがあります。これにより「くも膜下出血」を起こすことがあります。 - ➤ 一過性脳虚血発作(TIA)・虚血性脳卒中
一時的に脳への血流が減少し、めまいや手足のしびれなどの症状が起きることがあります。持続する場合は脳梗塞(虚血性脳卒中)となります。 - ➤ 血栓後症候群、神経学的後遺症、死亡
血栓による合併症から、脳機能に後遺症が残ったり、重篤な場合には命に関わる可能性もあります。 - ➤ 痙攣発作・けいれん
脳への刺激や炎症により、一時的にけいれん発作が生じることがあります。 - ➤ 水頭症
くも膜下出血などの影響で、脳脊髄液の流れが滞り、脳室が拡大する状態です。 - 📌【血流や血管の変化に伴うリスク】
- ➤ 血管攣縮(れんしゅく)
血管が収縮して一時的に血流が減少し、頭痛や脳虚血の症状を起こすことがあります。 - ➤ 血管再生
瘤の入り口や治療部位に新たな血流経路ができ、再発のリスクにつながる場合があります。 - ➤ 動静脈瘻(どうじょうみゃくろう)
動脈と静脈が異常につながることによって、異常な血流が発生します。 - 📌【全身的・その他の症状】
- ➤ 頭痛、吐き気、嘔吐
治療後に一時的に起こることがあり、多くは経過観察で改善します。 - ➤ 脳以外の臓器への虚血
血栓や塞栓が脳以外に流れた場合、他の臓器の血流障害が生じることがあります。 - ➤ 感染症
挿入部や血流を通じて感染が起こる可能性があります。抗菌薬の投与などで対応されます。
✅ 安全に治療を受けるために
これらの有害事象は、すべての患者さんに起こるわけではありません。
治療前に行われる画像検査や問診により、医師がリスクを評価し、患者さん一人ひとりに適した治療かどうかを判断します。
また、治療後も数日間の経過観察と定期的な画像フォローアップにより、安全性を確保する必要があります。
✅ リスクを理解したうえで、適切な治療選択を
Woven EndoBridge(WEB)治療は、従来の治療が難しかった動脈瘤にも対応できる、画期的な治療法です。
しかし、低侵襲とはいえ一定の合併症リスクを伴うため、事前にしっかりとした説明と同意(インフォームド・コンセント)が重要です。
まとめ:WEBは脳動脈瘤治療の新しい選択肢
くも膜下出血を予防するには、早期に脳動脈瘤を発見することが大切です、重篤な病態になることを1回のMRI検査で防ぐことができる可能性があります。
脳動脈瘤は治る病気のため、未然に防ぐことが大切です、脳動脈瘤がある方は、当院でのMRI検査で発見され治療のきっかけとなる事が望まれます。
現在、いろいろな治療法も出ており、一つの治療法ですべてをカバーすることはできませんが、上記のようなデバイスにて、治療の範囲が広がり、適応の可能性がある場合は、適切に治療できる医療機関へのご紹介の幅も広がりました。
WEB治療の対象かどうか、ご不安な方もまずは当院へご相談ください。必要に応じて、専門の医療機関と連携し、最適な治療につながるようご紹介いたします。
※本記事は勝川脳神経クリニック 院長 青山 国広 医師(日本脳神経外科専門医/日本脳卒中専門医/頭痛指導医)が監修しています。
監修日:2025年4月16日
▶監修医師のプロフィールはこちら